- ラーニング >
- メソッドの設定と実行 >
- 基本的な定量メソッドの設定 >
- 内標準
内標準の詳細
内標準は分析の一部として使用できます。このページでは、以下の情報を提供します。
- 内標準を使用する必要があるのはなぜですか?
- 内標準はどのように適用しますか?
- 内標準はどのようなマトリックス効果を克服できますか?
- 内標準はどのように選択しますか?
- 内標準が持つべき特性には他に何がありますか?
- 一般的な内標準の例にはどのようなものがありますか?
- 内標準はどのように標準液とサンプルに添加しますか?
- 内標準を含む ICP Expert では、どのようにメソッドを設定しますか?
- 内標準比はどのように表示しますか?
- 内標準法にはその他のメリットがありますか?
内標準を使用する必要があるのはなぜですか?
内標準法は、サンプルマトリックスによる強度の変化や変動(ノイズ)の影響を補正するために使用する方法です。そのため、内標準を使用すると分析の真度と精度の両方を向上させることができます。
内標準はどのように適用しますか?
内標準法は、最初のブランク(または標準液)で測定した内標準の強度を取得し、それを 1.0 として参照することにより適用します。後続の標準液とサンプル中の内標準の強度は、最初の内標準の測定値に対して参照され、比率として計算されます。この比率を後続の標準液とサンプルの計算された値に適用し、補正値を導出します。つまり、検体用標準液とサンプルは、内標準と検体の両方に影響を与える可能性のあるすべての変化に対して補正されます。
内標準はどのようなマトリックス効果を克服できますか?
内標準を使用して克服できるマトリックス効果には 2 種類あります。
- 標準液とサンプル間の粘性の差による影響。粘性の差は、プラズマへのサンプル移送率に変化が生じる原因になります。
- プラズマ中の励起状態に及ぼすサンプルの影響。
プラズマへのサンプル移送率に変化を生じさせるサンプルマトリックスは(影響 1)、ほぼ必ずプラズマ中の励起状態に差を生じさせ(影響 2)、その逆も同様です。そのため、粘性の差の影響をプラズマ放電そのものに及ぼす影響から分離することは困難です。結果として、内標準は通常、両方の影響を補正する目的で実行されます。
内標準はどのように選択しますか?
- 移送の差を補正するために、適切な任意のリファレンス元素を使用できます。
- プラズマ状態の差の影響を補正するには、検体と同様の分光特性を持つリファレンス元素と線を使用する必要があります。
そのため、内標準を選択する際に、次の点を確認する必要があります。
- 内標準と検体の特性が、可能な限り厳密に一致していること。内標準と検体の特性が一致していると、プラズマ状態で生じる変化は、検体と内標準に同様に影響するようになります。対照的に、これらの変化は原子線とイオン線に異なる影響を与える可能性があります。
- 内標準線のイオン化状態と励起エネルギーを検体の線に一致させます。一次近似では、線の励起状態のエネルギーは、同様の波長の線を選択することにより一致させることができます。したがって、同様のイオン化状態と類似した励起エネルギー(波長)を持つため、Mn II 257.610 nm の線は Fe II 259.940 nm に対する内標準の良い選択となります。反対に、Cu I 324.754 nm の線は Fe II 259.94 に対する内標準の良い選択ではありません。イオン化状態が異なり、そのエネルギーも非常に異なるためです。
内標準が持つべき特性には他に何がありますか?
内標準は次の追加の特性を備えている必要があります。
- 内標準はサンプル中の検出可能量で存在してはなりません。
- 内標準はサンプルからのスペクトル干渉の影響を受けてはなりません。内標準へのスペクトル干渉が発生したときは、容易に補正できる必要があります。
さらに、内標準自体が検体にスペクトル干渉を発生させてはなりません。 - 内標準液は、検体溶液やサンプル溶液と化学的に適合している必要があります。
- 内標準は純物質として入手する必要があります。
一般的な内標準の例にはどのようなものがありますか?
ICP-OES での内標準法に使用される一般的な元素には、Sc、Y、La、Lu などがあります。これらの元素が汚染物質中に存在することはほとんどありません。唯一の例外は Y であり、一部の環境サンプル中に存在します。
内標準はどのように標準液とサンプルに添加しますか?
内標準は標準液とサンプルに添加する必要があり、内標準の濃度は一貫して一定に保たれる必要があります。これは、内標準を各溶液に手動で添加するか、3 チャンネルポンプの 3 つ目のチャンネルを使用することにより実行できます。
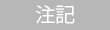 |
希釈を実行し、手動で溶液を内標準でスパイクした場合、希釈液には内標準が溶液中の濃度と同じ濃度で含まれている必要があります。そうでないと不正確な結果が報告されます。 |
内標準比はどのように表示しますか?
内標準法にはその他のメリットがありますか?
はい。内標準法の最終的なメリットは、分析対象物と内標準を同時に測定するときに生じます。
分析対象物と内標準の同時測定によって、フリッカノイズとして知られるノイズを補正できます。これは、分析対象物強度の変動(たとえば、プラズマへのサンプル導入速度の短周期変化によって生じたもの)は、内標準の強度にも継承されるためです。そのため、比率算出により分析対象物の強度に対するサンプルマトリックスの影響を補正するのと同様に、強度の比率算出を使用して、短周期変動を補正できます。この比率算出は、ノイズがフリッカノイズにより制限される線の分析精度(RSD)の向上につながる可能性があります。